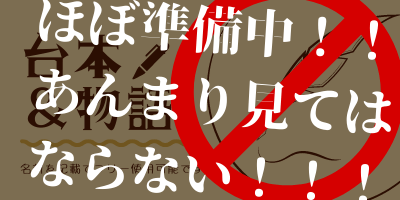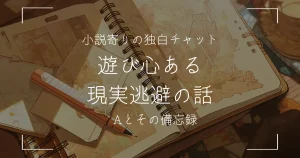詩と小説の中間の読みもの
少年が大好きな少女と、
少女の想いを知りながらも彼女を好きになれない少年の話。
拝啓 神様、出来損ないの僕。
「また振られた? ……っ、
じゃあ、お祝いに何処かいこっか!」
明るい笑顔を浮かべ微笑んだ彼女は、
瞳を左右に揺らし、僅かに唇を震わせて、
声を作らず、
結んだ。
言いかけた言葉が少し気になる。
けれど、それは聞くべきことだとは思わない。
だから、ただ、彼女が言いたい言葉だけを
聞くことにしたんだ。
桜の花弁が、雨と共に落ちていく。
ひらいていない蕾まで、
落ちて、
散る。
ビニール傘越しに、その様子を眺めて、
白い息を吐いた。
また、彼女は唇を震わせる。
ああ、やっぱりだめだ。
このまま、彼女の言葉を聞けないなんてことは。
僕は、彼女の言いたいことを聞くことにした。
「それで。言って」
「言って……って?」
「僕にして欲しいこと、ちゃんと、言って欲しい」
まっすぐな視線を彼女に向ける。
そうすると、
大きな瞳をゆらゆらと揺らす。
悩んだ末に、
その瞳は真っ直ぐに
射抜く様に僕を刺した。
そして、次の瞬間、

雨の降りしきる中。
彼女は、まるでゴミを捨てるように、
傘を投げた。
それで一歩ずつ、僕に近づくと嬉しそうに、
寂しそうに微笑んで、
優しくて、温かい腕で、大きく包み込んでくれた。
頭をなんども優しく撫でて、
後頭部に小さな口付けを落とし、
輪郭を覚える様にゆっくりと手を滑らせて、
僕の頭を撫でていく。
甘えているのか、甘やかしているのか。
嬉しそうな吐息がそっと零れ落ちるものだから、
彼女が満足するまでされるがままになった。
名残惜しそうに、
てのひらを離して、人差し指を離す。
その後に、残念だな、と
少し口惜しそうな言葉をこぼした。
この次の言葉を、僕は知っている。
だから、それに
ごめんねを伝えるように
頭を撫で返した。
彼女の様な甘くて優しい撫で方は、
恋愛感情がなければ出来ない。

そうだ、僕は、
女の子のことが好きになれないのだ。
それなのに、彼女の好意を知ってしまっている。
彼女は悲しそうに微笑んだ。
「君が、女の子がすきだったら良かったんだけどな」
すこし涙声で答えた言葉は、明るいからこそ
悲し気に聞こえる。
僕も、これだけ彼女からの
大好きをもらっている。
彼女の沢山の
愛してるをもらっている。
彼女と一緒であれば、
きっと、しあわせなんだ。

そんな未来があれば、本当なら良かったんだ。
けれど、僕は。それが、出来ない。
同性愛と言われると、
それも、それで違和感がある。
実際はその通りに見えるのかもしれないけど、
好きになってしまうのが、
気付いたら
異常な恋だった
というだけで。
僕は、彼女をすきになりたい。
分からない。
彼女の傍にいたいのに。
心が震えることなんてない。
縋ってでても、一緒に居たいと思うのが恋で、
毎日挨拶をするだけで胸が苦しくなるのが恋で、
視線が合うだけで高揚感に包まれるのが愛で。
彼女から、それを全く感じない。
でも、僕は彼女を好きになりたくて。
大好きになりたくて。
おかしい。
頭上からゆっくりと落ちていく雨粒と、
僕の頬をゆっくりと落ちていく雨粒。

「僕だって、好きになりたい」
声にしたら、
その言葉は鮮明になっていく。
鮮明になるからこそ、
心に痛みが走って、喉に杭が刺さって、
声を出したくても、
声が震えてしまうんだ。
「そう、好きになりたいんだよ。
なりたいんだ……でもっ、
きみは……
ちがう…から…っ」
僕は縋る様に、彼女の頭を撫でる。
抑えきれない情けない泣き声、
耳を塞ぎたい。

でも、これが初めて彼女に伝えた本音だった。
毎回、振られていることを知っている彼女を
代わりの様に好きになりたくはない。
本当に彼女を好きになれるなら、
ずっと一緒にいたかったのに。
彼女は、
まるで知っていたかのように
驚かなかった。
僕のこころに寄り添うような温かい表情で、
気付かれない様に
涙を流した。
ただ、僕の頭を撫で返して、
小さな声で
「ありがとう、だいすき」
と言ってくれた。
その声が優しくて、
でも、
その唇はまた、
震えていた。
神様、分からないです。
僕は、彼女がすきになりたい。
どうしても、好きでいたい。
好きになった方が、
本当に、ふたりとも幸せなのに。

どうして、こんな意地の悪い世界と、出来損ないの僕を作ったのですか。