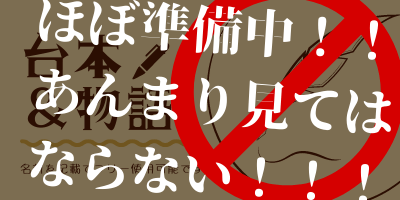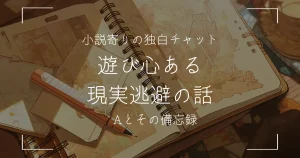親指姫モチーフのメリーバッドエンド、あるいはネバーアンハッピーエンド。
)
少女の独白A

この世界は事実しか知らなくて
本音は知らない。
それでいいと思っていた。
だからこそ、
こんな形での平和だってつくれた。
私は誰よりも冷徹で、
誰よりも残酷で、
触れてはいけない存在。
みんながそう思ってくれれば、
誰もが怖がって、
この秋の森に入ろうとすら思わなくなる。
子どもっぽいと思ったその作戦は、
思ったよりも簡単に成功してしまった。
だから、この森は、
けして戦争なんて起きない。
みんな、私が怖いから。
この世界は
事実しか知らなくて、本音はしらない。
好都合なことだと思った
でも、少しだけ笑わないことに
疲れてしまった。
歌わないことに疲れてしまった。
だから、
一つだけ、
どうしても叶えたいことがあったの。
私のことを知らない友達が、
誰も知らない友達が欲しかった。
Happy ever after
わたしの身体は、親指ほどしかない、
とても小さな小さな体をしている。

お父さんもいないから、
変だなって言われる。
お母さんと、わたし。
ふたりきり。
でも、しあわせな毎日。
みんなに不思議だと言われるから、
お母さんに聞いてみたの。
「どうして、わたしは、ちいさいんだろう」
「どうしても、女の子が欲しくて、
魔女からお花の種をもらったの。
それで、その可愛い可愛いお花から、
生まれたのが貴方なの」
それからは、もう。
二人っきりであることも、
身体がみんなより小さいことも
どうでもよくなった。
だって、お母さんが
わたしを望んでくれている。
それだけで、うれしかった。
お母さんは手の平に、
小さなわたしを載せる。
わたしは、その大きい頬を両手で包んだり、
頬と頬を擦り合わせたりした。
お母さんの為に練習をした唄を歌えば、
優しい目がもっと優しくなる。
それで、さびしいことなんて
本当に何一つとてもなくって。
毎日こんな日々が続くなら
しあわせだと思って、
明日も一緒に何をしようって思って眠って、
⁂
夏の森。蛙、帰る場所の違いの話
その朝。

目の覚ましたのは、湖の上。
黄金の太陽の光が湖に揺れて、
細やかな夏の光が輝いている。
蝉の声が反響し、
色鮮やかな大きな花々が水辺を飾っている。
此処は、夏の森なのかもしれない。
わたしがいた秋の森からは、
少しだけ離れた温かく穏やかな世界。
わたし自身は蓮の葉の上にいて、
ゆら、ゆら、
と不安定に揺れ、
わたしの目も、不安で
ゆら、ゆら
と揺れてしまう。
⁂
お母さんを探した。
分かっていたけど、いない。
目の前は、大きな湖が広がっている。
少しだけ勇気を出して、
ジャンプしたとしても
飛び越えれない大きな大きな湖。
この状況をどうすればいいんだろう。
喉が渇いてしまいそうになるほど
陽の光は降り注いでいて、
湖の水を掬いあげて飲もうとした。
すると、その水に、
気弱そうな蛙の男の子が映っていて、
思わず後ろを振り向く。
わたしを近付いて、じっと見つめて。

わたしは一歩下がりたかったけど、
下がったら水に落ちてしまうからとどまった。
男の子の瞳が、わたしの瞳と重なる。
実は、蛙くんは月色の
優しそうな瞳をしているのだと気付いて、
ほっとした
けれど、伝えられた言葉は
ちょっと分からない。
「今の暮らしは、可哀想だと思ったんだ。
これからは自由なんだよ」
分からなかった。
何が可哀想なのかもわたしには、
理解できなかった。
でも、わたしが好きだった場所を、
遠ざけたのはきっとこの人だと、
すぐに分かった。
ちょっと怖いけど、
蛇みたいに睨んでみると、
「ひっ」と言って男の子は怯んだ。
良かった。
でも、そんなに怯えた表情をしていても、
勇気を振り絞ったのか蛙くんはつづけた。
「きみの為に、
きみの好きなものはいっぱい揃えたよ。
きみの家だって、昨日頑張って作ったんだ」
そう言って、
蓮の花で作った淡い赤色の家を見せてくれた。
丁寧に、丁寧に作ってくれたことは良く分かる。
そっと中を覗いてみた。
たんぽぽの綿毛で作った柔らかい椅子、
うさぎの毛をいっぱい集めたふかふかの布団。
きらきら、光る綺麗な湖が、
まるっと見渡せる大きな窓。
お母さんと住んだ大きな家とは、ほど遠くて、
わたしの大きさに全てがぴったりな小さな家。
この人が、わたしの為に
作ったんだなってことが確かに伝わってくる。
でもね、可哀想は
やっぱりどうも分からない。
お母さんはとっても怖い人、
お母さんはとっても酷い人。
そうやって言われてるのは、
知ってないわけじゃないの。
でも、だからと言って、
わたしの前では怖くなかった。
酷くもなかった。
それだけで、
充分だと思うし、
全ての前で良い顔をする方が
不思議だと思うの。
きょろり、とした、けれど優しい目が
見つめてくる。
否定を怖がるような目、
きっと受け入れて欲しくて
この子は頑張ったのかも知れない。
けれど、その受け入れる。という言葉は、
わたしじゃなくてもいい。
そんな気がした。
此処を離れて、お家へ戻らないといけない。
だから、一瞬だけ安心してもらって、
男の子の目を反らしたかった。
少しだけ微笑んで
「気に入ったわ、ありがとう」と嘘を吐く。
そうすると、凄く安心したように、
大きな溜息を吐いて、
不器用な笑顔で笑った。
少しだけ、心が痛んだ。
けれど、此処じゃない。
何よりも、待っている人もいる。
やっぱり、
蛙くんの思う可哀想と、
わたしの思う可哀想は違う。
夏の森。大丈夫って、不便な言葉な話
⁂
生まれてから泳いだことなんてなかったけれど、海の様な湖に飛び込む。
身体中に、冷たさと、
水の飛沫がいっぱい纏わりついて擽ったい。

目を開くと、透き通った水色の世界に、
七色に色を変えて踊る様に泳ぐ魚達。
その泳ぎ方を少し真似して、湖を渡っていく。
わたしの小さな手が土を掴んだから、
そこで顔をあげた。
気付けば、
とても気温が冷たかった。
此処は、夏の森の隣の冬の森。
少しお母さんから
遠ざかったしまったことは悲しいけれど、
夏の森から抜け出せたことで安心していた。
冬の森はとても暗くて森、
梟の声が良く聞こえる森だった。
真っ暗で、寂しくなったから唄を歌って、
少し曲がっている道を歩く。
お母さんも必死で探してるんだろうから、
会いに来てくれるかな。と思ってる。
だから、大丈夫。
怖くない、寂しくないよ。
…会いたいよ。
少しよぎってしまった哀しいことが
だんだんと大きくなってしまったから、
考えるのを止めた。
悲しくない様に、また唄をうたった。
それはお母さんが歌っていた歌。
お母さんが子守歌を歌ってる時、
途中で声が震えて、
詰まることもあったのを思い出した。
けれど、寝てるフリをしていたし、
困ってることは聞かない方が良いと思って、
悲しいけれど、
わたしの為に
歌ってくれる大切な歌を聞いていた。
⁂

歌をうたいながら進むと
段々暗い所に目は慣れてきたけれど、
ぱら、ぱら、と雪が降ってくる。
白くて、触れたら溶けてしまう様な雪だったけれど、
進めば進むほどその雪は、
粉雪から、
ぼたん雪に変わって、
どんどん、この森に降り積もっていく。
気づいたら、足元は雪で覆われている。
後ろを振り向くとわたしの足跡が映っていた。
白い世界は、
とても綺麗だけど、
何もない様な気がしてしまう世界。
すこし、寒いけれど、寒くないよ。
冬の森。誰かの代わりになるなんて、お互いにできない話
⁂
凍えそうな身体を、
両手で抱き締めながらゆっくりあるくと、
小さな点が見える。
その点が、
だんだん大きくなって家の影になっていき、
その家の前で足を止めた。
小さな、
でもわたしにはぴったりの煉瓦造りの家。
煙突や屋根も雪が被っている。
家から零れる灯は、
この寒い寒い冬の森の中で、
唯一とても優しくて、
温かい。
その温かさを感じるから、
反対にじんわりと心の奥が寒くなっていく。

美味しそうなチーズスープの匂いもして、
一つの影がゆったりと動いているのが見えて。
こんな小さいところには、お母さんはいない。
けれど、この温かさは似ていて、
恋しくて、
だからね、寂しいんだ。
気づけば、わたしはその扉を、
3回叩いていて、自分でも驚いて目を丸くした。
その扉を開けて出てきてくれたのは、
わたしより小さなネズミのお姉さん。
銀色の星の様な髪をした綺麗な雰囲気がある。
「どこから来た子かしら?」
「家から来たの」
「帰りたいの?」
「うん、帰りたいよ」
「……そう、」
穏やかで温かい声、
けれどどうしてだろう。
何処か悲しい声をしていた気がして、
なにかを隠してるようだった。
このお姉さんも、また。
わたしと、お母さんの知る人だとすぐに分かった。
ねずみのお姉さんを温かく抱き締めた。
それで、お母さんの声に寄せて伝えてみる。
「大丈夫だよ」
自分で思うよりも、
優しくて、穏やかな声が響いた。
うん。わたしが、大丈夫というのもちょっと変かも。
でもね、わたしが悲しい時はね、
そうやってお母さんがしてくれたんだ。
そうすると、大丈夫じゃなくなるの。
つらい、かなしいが
いっぱい溢れ出るの。
心に隠していたことがぜんぶ、出てくるの。
こんな優しい魔法、本当にないと思ってる。
そのお姉さんは泣くことはしなかった。
でも、肩口に顔を埋めた。
感情が溢れて止まらないのかなと思った。

そういう時は、ぜんぶ出し切った方がいいの。
⁂
それから、ちょっと落ち着いたのかな。
お姉さんは埋めていた顔を戻すと、
赤くなったうさぎみたいな目で微笑んでくれた。
少しだけ瞳を右、左、と動かして、
震えた唇を閉じて、開けて、をしてから
戸惑いながら、わたしに聞いた。
「……良かったら。
ちょこっとだけお姉さんが
お母さん代わりをして、いい?」
不安げな声、けれど希望を持った声で聴いてくるお姉さん。
代わり、なんてない。
けれど、このお姉さんが寂しいって思ってるのは伝わったし、
わたしも寂しかったから、
ふたりぼっちになることにしたの。
それから、一週間ぐらい。ふたりぼっちでいた。
でも、ちょっと違ったの。
外に出ようとしたら、
外は危険だからってすぐ止められて、
家の中に閉じ込められたように暮らした。

寂しいと寂しいは、
もっと寂しいになった気がする。
大切に大切にしてくれた。
けれど、お母さんとは撫で方も違う。
眠る時の歌う声も全然違う。
温かい部屋はとても暖かいけれど、此処はわたしの部屋じゃない。
おままごとの様な感じの可愛いだけの、生活。
薄暗い森の中では苦しいもないけれど、楽しいも新しいも見つからない。
お母さんといる時はね、
一緒にどっちの紅葉の葉が色変わるが競争したり、
一緒に虫さんの姿が変わる様子を見たり、
一緒に育てた野菜が食べられてて怒った気持ちなったり。
でも、この生活には
一緒に笑ったりしなかった。
一緒に泣いたりも、そういうのがなかったの。
大事なものに触れてはいけない様な感じで、大切に大切にされた。
けれど、それは、道具を大事にしてるような感覚で。
きっと、わたしはお姉さんの何かを埋めるだけの道具。
わたしの心を見てる気がしなかった。
だから、少し迷ったけれどお姉さんを、
まっすぐに見つめて、本当のことを伝えることにした。
「もう、お母さんごっこは、やめても良い?」
「ごっこ…?」
まるで、蚊がなくよりも小さなささめき声。
驚いた様な、縋る様な悲しい声で呟いたお姉さん。
でもね、わたしは頷いた。
ちゃんと聞こえる様に、もう一回言う。
「ごっこ。」
「でも、わたしなら、もう貴方を連れ去らわれるようなことはしない」
「お姉さん。ずっと一緒はね。
……かえって、とっても寂しかったな」
そう伝えると、わたしはまた寂しくなって。
お姉さんも寂しくなって。
涙は流れてない。
たぶん、ふたりして強がりだったの。
今日は、子守唄を歌わなかったから、わたしが歌うことにした。
「今まで、ありがとう。」
そう言って、微笑んで、お姉さんは眠った。
本当は一緒に居れればよかったんだろうけど、
やっぱりふたり一緒なのは寂しくなるだけだったのかな。
だから、これで良かったんだと思う。
少しだけ腫れぼったくなっていたお姉さんの瞳に、
キスを落として、わたしも眠ることにした。
冬の森。嘘は信じ込ませる為にある真実ばかりな話
⁂
「今日はね、
ちょっと話がしたいって人がいたから呼んできたの」
翌朝、そう言ったお姉さんの言葉は本物の声をしていた。
晴れ晴れとした声には、寂しさもあったけれど、
もうわたしが触れるべきではないと思った。
静かなノック音がして、お姉さんはその扉を開けて
その人を向かい入れた。

目に包帯をしてて、
艶のある真っ黒なコートを着た
背の高いモグラの男の人だ。
足音や、気配でわたしがいることは分かるみたいで、
まるで見えてるようにじっと此方を見た。
「……あの森で歌っていたのは、」
「うん、」
地を這う様な落ち着いた声で淡々と聞くモグラさん、
不思議に思うけれど今は頷くしかなかった。
「秋の森で歌っていたのは、」
「……。」
これは、また。きっとわたしのことを知っている人なんだろう。
何となく、気付いたこと。
お母さんはとっても有名だから、
わたしも知られてしまっているのかもしれない。
少しだけ考える素振りをしてみたけれど、
やっぱり変なことを伝えるべきではない。
「うーん、違います。帰って下さい」
「確かに、その声だった」
違う、と伝えたけれど、声で判断されてしまった。
石で出来た椅子に座ると、
その背の高いモグラさんと向かい合う状態になる。
モグラさんは両手の指を合わせたり、
離したり、して少し考え込む仕草をする。
指を重ねると、口を開いた。
「きみは、自分が普通じゃないのは知っているかな」
少し不機嫌な顔をしてわたしは頷いた。
けれども、
盲目のその人には見えていないと思う。
「知っていると思うけど……
きみのお母さんは、とっても悪い人なんだ。」
続けた言葉に、
わたしは首をかしげて、
くすりと笑った。
可笑しい。
みんな、わたしを可哀想。
お母さんは悪い人。

と嘘を吐く。
実際に会ってしまったのなら、
そんなこと思えなくなるはずだもの。
お母さんは、あれでも、とっても嘘が下手なのに。
「だから、きみを皆で守ろうと思って、あの部屋から連れ出した」
「何も、知らないのにそんなことを言うのね」
お姉さんと男の人は顔を見合わせた。
まるで、わたしを不思議だと思っている様。
わたしは、何も知らない。可哀想な子。
そうは、わたしが思えない。
「自由になったのに、嬉しくない?」
「? 何を言っているのか分からないわ」
「ああ、そうか。自由でも、何処にも行くことが出来なかった」
そういうとモグラさんは、
大きなコートから金色の硬貨を数枚取り出した。
「これは特殊なお金でね、これがあれば何処にだっていけるし、
何でも食べる。大体のものはこれがあれば出来るよ。」
「なら、お母さんの家に」
「それが危険だと言っている」
「そればっかり」
「だから、皆は君を迎え入れたいと思ってこうやって話してるんだ」
「うーん、みんな自分が、したいことをしていた。
様に見えたわ」
「なら、俺は君の眼にどう見えてる?」
「まだ分からないけれど、わたしの為ではないわ」
「……これは。仕方ないな、諦めよう」
そう言うと、黒いコートを翻して、扉を開けて出ていこうとした。
他の動物たちよりも、
あっさりと引いてくれて、わたしの方が瞬きをした。
嘘吐いて逃げたり、真正面からお話をしなくても、
何故かこのモグラさんは引いてくれた。
「早いのね」
「通じないお子様と話す程、無駄な時間はないからね」
「お話は通じるわ、通じないのは大人の方じゃない?」
「では言い換えようか。
情けなく長引くのは愚か者がやることだ。
ああ、でも。」
そう言って、見えないはずの目で、
わたしをまっすぐに見て、
少し唇の口角をあげて、懐かしむような声で伝えてくれた。
.
「君の歌は好きだったから、
近くで聞いていたいとは思ったよ」
「そう、ありがとう。
でもね、」
わたしも、その目に応えたいと思って、
その目を真っすぐに見つめた。
人形の様に作った小奇麗な笑みで、
少し悪戯な眼をして、
本当のことを伝えるの。
..
「――あなたが聞いていた声、
お母さんの声だと思うの」
盲目の男の人は、
小さく「えっ」と
驚きを隠せない表情をした。
それがおかしくて、
お姉さんも困惑した状態でいる。
悪逆非道の冷酷なあの人は、
あなたの好きな歌声で口ずさむの。
だって、お母さんは、とても優しくて。

わたしより、少しだけ大人なかわいい女の子だもの
呆然としている二人の間を抜けるように、
わたしはスカートを翻して、この部屋を抜け出した。
冬の森。季節が変わる前がいちばん寒さを感じる話
⁂
扉を開けると、北風がわたしの身体の全身を蝕んでいく。
そうだった。
わたしは、さっきまで冷たい冬の森にいたんだった。

凍えそうな身体を、一歩ずつ前へ、前へ、と進んでいく。
ふわふわ、と睡魔が身体を死へと揺さぶる。
.
足は凍えて痛い程なのに、
感覚がなくなってきて、少し熱くなってきている。
.
それでも、ネズミさんとモグラさんのいるあの家は
わたしの帰る所じゃないから。
この冬の森を抜ければ、温かい春の森があって、
それを抜ければ、やっと秋の森へ帰れるんだから。
半分、朦朧としてしまった頭で、でも、絶対に倒れはしないと決めて、
冷えた氷柱の雑木林の中をゆっくりと入っていく。
道端で、雪に塗れたアネモネが、
ゆらゆら、と揺れている。
今、眠くなって
ゆらゆらと揺れているわたしみたいだったから、
アネモネに近づいてみた。
すると、そのアネモネが
温かい風で揺られていることに気付いて、
目を丸くした。
.
春の森からの風だ。

眠くて、苦しくて、もう倒れそうだった足は一気に軽くなった。
.
重い瞼も一気に開いた。
.
アネモネが揺れている方向、
春風の向きを頼りに、
春の森へと続く道をゆっくりと、歩いていく。
⁂
.
春の森。わたしが、王子様にならないと意味がないって話
温かな世界の中、
だんだんと氷柱の雑木林が
溶けていくようになくなっていて、
真っ白だった床も気付けば、
黄緑色の芝生が生えている。
.
小さなかわいらしい花も咲いていたり、
たんぽぽの綿毛がふわふわ、と
色んなところを飛び回っている。
.
曇り空も消えてきた、
優しく真っ白なお日様の光が降りそそいでいく。
その光を、色とりどりの花々が浴びていく。

ゆらゆらと燃えるような赤色の花、
ふわふわとしていて雪の様な白い花、
神秘で、静かな涙のような青い花。
少し大人っぽい紫の色なんてお母さんに似合うかもしれない。
.
その色たちは、とても優しかったり、
暖かったり、
冷たかったり。
いろんな感情があった。
.
楽しくなって、とても疲れていたことも忘れて、
右にも左にも咲いているお花を眺めて、
前を見ずに歩いてみた。

案の定、目の前にあった花にぶつかって、
ふわり、とした感触がして、転んでしまった。
「ごめんなさい」
「うん、本当に」
謝ると、お花にぶつかったはずなのに、
返事がかえってきた。
.
不思議に思って顔を上げると、
その花の中にいる
小さな男の子が声をかけてくれていた。
.
その花に似た雪色の髪をしていて、
その真赤な眼は椿のようだった。
.
その子はしゃがみこんで、手を差し出したから、
その手を握り返して、起き上がる。
.
右手で、わたしの身長と男の子の身長を確認する。
そんなに身長が変わらない。
.
さっきまでは、
カエルさんやねずみさん、
モグラさんとかの動物だったから
似た身長だっただけなのに。
.
人の形をしていて、
おんなじ身長をしている。
.
不思議に思っていると、
くすり、と潜めた笑い声で笑われた。
.
「可笑しいのは、きみの方だけだろ」
まるで揶揄う様に、わたしの鼻を詰まんで、
楽しそうに笑みを浮かべられた。
.
よく見ると、男の子の背には
七色の透き通った羽根が生えている。
.
あんまり聞いたことがないけれど、
きっとこれが妖精というの、かな。
.
それにしても、また。
きみは、可笑しい。と言われた。
.
「妖精さん」
「ご用件を」
「また、あなたもお母さんが悪いと言うの?」
.
わたしがそう言うと、
.
赤い瞳はわたしの感情を見抜くように
まっすぐに見つめてから、
納得した様に相槌を打った。
「……やっと、状況を理解した」
.
「みんな、必死なのね」
「きみが当事者だ、他人事をしてやるな」
.
「わたしには関係ないこと。
他人が騒いでいるだけ」
「他人が他人の都合で、動いているだけと。
君は、戻りたいと。」
「初めから、
ずっとそう言っているのに誰も聞いてくれない」
「君の声を求めてる者が、いないんだろうね。
他人事だろうから。」
「やっぱり、他人事なの?」
「他人事だろうけど、口実に使われたようだ。
うん、これは面倒だ。」
「面倒?」
「元々あのお母さんには悪い噂が立ってるから、
「可哀想な子がいるから守ってあげよう」
と言い訳をして
捕まえようとしている。」
「そこまでは、知っているわ」
「なら、その可哀想な子を救うために、
お母さんをどこかへ飛ばそうとしていることは?」
「え」
「改めて聞くけど、君はこれを望んでいる?」
「そんなの、望んでない。」
「なら、僕は止めない」
「さようなら、早く戻らないと。」

居ても立ってもいられなくて、
わたしはその妖精さんを横切っていた。
⁂
秋の森。わたしも、寂しかっただけの話
わたしは、わたしだけが大変な状態だと思って、
早く帰らないとと思っていたけれど。
.
いま、いちばん危険なのはお母さんだ
お母さんがどういう人かなんて、わたしがいちばん知っている。
.
だから、みんなが言っている言葉は、
まるでお母さんを捕らえたいだけの言い訳で、
わたしが可哀想だなんて、誰も思っていない。
.
それを妖精さんは教えてくれて、
背中を見届けてくれている気がした。
このままではいけない。
.
暖かった春の森を、小さな小さな身体で一生懸命走って、
たまに疲れて休憩して。
お腹が空いたら、蜜を飲んで。
.
そうやって、
3日かけて、春の森を抜けて。
また、暑い夏の森を抜ける。
.
ちょっと、足が火傷してしまったけれど、
急がなければいけない。
.
わたしが何が出来るか、なんて考えても
わたしは何も出来ない。
.
けれど、
こんなにも、ひどい事を言われているお母さんを
ちゃんと大好きだよって言う事が
できるのはわたしだけなんだろうなって思ったから。
.
そうやって、一生懸命走って、走って、
.
自分の足で、秋の森へ着いたのは
一週間も経ってしまった時のことだった。

⁂
秋の森は誰もいないかのように、
しん、と静まり返っていた。
.
それだけで、少しだけ嫌な予感は過る。
此処からどうやって家に帰ればいいかわからなくて、
道を彷徨うだけ彷徨った。
.
息を整えてから、また走って、見渡して。
.
大きな楓の樹が立っているところの近く、
探せば見つかるはずなのに。
.
急いで探そうとすると、
あの目立つ楓の樹が一向に見つからないの。
.
もしかして、見えない様な魔法が貼られていたら?
その考えが過ってしまって、足が止まってしまった。
.
きっと、そうに違いない。
でも、いても立っても居られない。
でも、一度止まってしまった足はもう動かなくなっていて。
.
火傷して、
霜焼けもして、
真っ赤になった足が痛い。
.
気付けば、夜になってしまっていた。
.
どこか安全なところで寝ないと、と思っていると
綺麗な桃色の違う秋蛍がふわり、ふわり、と浮かぶ。
.
見覚えがないはずなのに、
とても懐かしい気がした。
.
その不思議な色の蛍は近付いて、
わたしの指先にそっと乗った。
.
「――おかえり、」
これは、お母さんの優しい声。
似ている。
.
ううん、似ている、じゃなくて、この声は。
.
そう思った瞬間、桃色の光がわたしを包む。
びっくりして、目を閉じる。
.
暖かな温かな感覚と懐かしい匂いに包まれた。
⁂
秋の森。何も知らない人たちについての話

開けるとそこには、
わたしがいつも眠っていたところ。
.
もしかして、これは全部夢だったのかもしれない。
すごく安心した。
.
ちゃんとお母さんに会えるんだって思うと、
本当に本当にうれしくって。
.
夢のなかであったこと、
いっぱいいっぱい話して、
ちゃんと伝えたいこといっぱい伝えよう。
.
いっぱい抱き締めて、
ちゃんと大好きだって伝えて、
周りの人がどれだけ酷いことを言っても
わたしは味方だよって伝えたい。
.
…でも、いつもはわたしが目を覚ますと、
真っ先にお母さんが「おはよう」って言うはずなのに、
ずっとお母さんがいない。
.
毎日使っていた部屋を行き来する移動の魔法を使って、移動する。
.
いつものお母さんがご飯を作ってくれるキッチンを見たけど
いない。
おやすみの前に本を読んでくれる寝室にも
いない。
遊んだり話したりする居間にも
いない。
.
かくれんぼをしている
――という、ことでもないみたい。
.
そうだ、きっとガーデニングをしているに違いない。
そう思って、庭へ行ってみる。
.
でも、そこにも
何もなくって。
.
そこで、やっと、
.
今までのことが夢じゃなかったと実感した。
.
可笑しい。
.
こんなことを、わたしは絶対に望んでいなかったのに。
わたしの為、
わたしの為、
と言って、
.
みんなが
わたしの
しあわせを
連れ去った。
.
確かに「おかえり、」というあの声は
お母さんの優しい声だったはずだったから、
.
きっとここにいると、
思ったのに。
.
あ、違う。
だからだ。
.
お母さんは、此処には来れなくなってしまったから、
わたしが戻ってきたときにだけ、
この家が見えなくなる魔法が解ける様にしてくれていたんだ。
.
お母さんのことをみんなは知らなかった。
.
もし、わたしが知らないだけで
お母さんがとってもとっても酷い人だったとしてもね
あの優しい声でわたしをこの部屋まで運んでくれた。
それだけで、充分だと思うの。
.
わたしはお母さんがとても大好き。
.
わたしはお母さんの隣にいるよりも、
妖精のようになった方がいい、と言われても、
.
お母さんはわたしを大好きだから生んでくれたのだから

お母さんが「おかえり」と言ってくれたのだから、
.
わたしは、ここにいたいと思う。
.
だから、
わたしは、
このお母さんが守ってくれた
やさしい世界にいたい。
.
誰が何を言っても、
わたしは本当にしあわせで、
.
わたしは世界でいちばんの、
たった一人の大切な人で、
おかあさんも世界でいちばんの、
たった一人の大切な人。
.
ただいま、お母さん。わたしはここに帰ったよ。
次は、わたしがおかえりって言いたい。
.
空がとっても明るいの。わたしはこんなに寂しいのに。
わたしのことなんて、あの空は見えていない。
.
お母さんが此処からいなくなって、
いい人になった人は喜んでいるのかもしれない。
.
だから、この空が晴れてるのなら、
雨になってしまえばいいのに。
.
土砂降りになって、
わたしのしあわせを取っちゃった人、
.
みんな
とんで
いけば
いいのに

なんて、
ちょっとね。
思っちゃったりする。